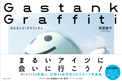乗り物の世界では、春は大掛かりなダイヤ改正の季節。都内の鉄道関係では、副都心線と東横線の直通や、秋田新幹線の新型車両登場などが話題となっていますが、路線バスにも毎年様々なダイヤ改正があり、時刻の変更のみならず、路線の新設・廃止・経路変更などが相次ぎます。そんな中、今回は3月末をもって惜しくも廃止となった、江戸川区の都営バス「春江町終点」バス停をご紹介します。
乗り物の世界では、春は大掛かりなダイヤ改正の季節。都内の鉄道関係では、副都心線と東横線の直通や、秋田新幹線の新型車両登場などが話題となっていますが、路線バスにも毎年様々なダイヤ改正があり、時刻の変更のみならず、路線の新設・廃止・経路変更などが相次ぎます。そんな中、今回は3月末をもって惜しくも廃止となった、江戸川区の都営バス「春江町終点」バス停をご紹介します。「○○終点」というバス停は、都営バスのお家芸的なネーミングで、かつては「浦安終点」「汐入終点」「足立流通センター終点」などがあり、いかにも場末の番外地にでも連れて行かれそうな、どこか郷愁の漂う行き先でしたが、これらのうち最後まで生き残ったのが[新小29]系統の「春江町終点」でした。いつか行かねばと思っているうちに月日は流れ、とうとう廃止の日を迎えるということで、桜の蕾もほころび始めた3月某日、都営新宿線一之江駅から「春江町終点」へと向かいました。

駅前の乗り場へ来てまず驚いたのは、運転本数が激減していた事実です。平日は一日9本、土日は7本という少なさで、以前はこんなはずではなかったと思うのですが、やはりこれでは廃止もやむなしということなのでしょう。小岩駅への京成バスが並走していることもあり、ここに都営バスが路線を開設した経緯はともあれ、その役目はとうに終了していたのかもしれません。事前に時刻を確認せずに来てしまったことが悔やまれますが、次のバスまで待ち時間が2時間近くある状況はいかんともし難く、ひとまず歩いてバスのルートを辿ることにしました。

[新小29]系統の路線図を見ると、メインは新小岩と葛西駅を結ぶルートで、一之江駅から春江町終点へ区間は枝線扱いとなっています。その区間、およそ1キロ。バスのルートとなる明和橋通りを歩き始めると、すぐに新中川を斜めに横切る明和橋に出ます。両端の4本の塔と、ほぼ半円形に近いアーチが独特の表情を見せる橋ですが、これを渡る都営バスの姿もあと数日限りと思うと、やはり一抹の寂しさを感じます。橋を越えると、その先は一直線の道路で、明和橋、春江町3丁目とバス停が続きます。いずれも京成バスとの共用なので、バス停そのものが無くなるわけではありませんが、もともと都営のバス停に京成が居候しているような体裁なので、4月以降はバス停の趣も変わってくるかもしれません。

やがて正面に瑞江葬儀所前の信号が見えてくると、その手前右手に都営バス専用の折り返し場が現れ、「春江町終点」に到着です。ここにもバスの姿は無く、背後の公園の緑に囲まれた広々とした折り返し場は、ひっそりと静まり返っています。一日9本のバスの為に、これだけの敷地を維持管理していくのも並大抵ではないでしょう。屋根付きのバス停には路線廃止を告げる看板が大きく掲げられていますが、これを読む人も僅かなのかもしれません。歴史を紐解けば、昭和30年代後半に東京駅からの路線として開業し、その後すぐに新小岩駅発着に短縮・変更されたものの、都営新宿線開通前の一之江周辺エリアの重要な足として長らく機能していましたので、往時はこの折り返し場にも次々とバスがやってきて、活気を呈していたものと思われます。

帰りのバスまで、まだあと1時間少々。もうしばらくこの折り返し場に、身を置くこととしましょう。廃止を惜しむ大勢のファンが詰めかけた東横線渋谷駅とは対照的に、人知れず静かに廃止の日を迎えようとしている「春江町終点」の姿は、じわじわと染み入るように私の脳裏に浸透し、記憶の印画紙にしっかりと焼き付けられていきました。


駅前の乗り場へ来てまず驚いたのは、運転本数が激減していた事実です。平日は一日9本、土日は7本という少なさで、以前はこんなはずではなかったと思うのですが、やはりこれでは廃止もやむなしということなのでしょう。小岩駅への京成バスが並走していることもあり、ここに都営バスが路線を開設した経緯はともあれ、その役目はとうに終了していたのかもしれません。事前に時刻を確認せずに来てしまったことが悔やまれますが、次のバスまで待ち時間が2時間近くある状況はいかんともし難く、ひとまず歩いてバスのルートを辿ることにしました。

[新小29]系統の路線図を見ると、メインは新小岩と葛西駅を結ぶルートで、一之江駅から春江町終点へ区間は枝線扱いとなっています。その区間、およそ1キロ。バスのルートとなる明和橋通りを歩き始めると、すぐに新中川を斜めに横切る明和橋に出ます。両端の4本の塔と、ほぼ半円形に近いアーチが独特の表情を見せる橋ですが、これを渡る都営バスの姿もあと数日限りと思うと、やはり一抹の寂しさを感じます。橋を越えると、その先は一直線の道路で、明和橋、春江町3丁目とバス停が続きます。いずれも京成バスとの共用なので、バス停そのものが無くなるわけではありませんが、もともと都営のバス停に京成が居候しているような体裁なので、4月以降はバス停の趣も変わってくるかもしれません。

やがて正面に瑞江葬儀所前の信号が見えてくると、その手前右手に都営バス専用の折り返し場が現れ、「春江町終点」に到着です。ここにもバスの姿は無く、背後の公園の緑に囲まれた広々とした折り返し場は、ひっそりと静まり返っています。一日9本のバスの為に、これだけの敷地を維持管理していくのも並大抵ではないでしょう。屋根付きのバス停には路線廃止を告げる看板が大きく掲げられていますが、これを読む人も僅かなのかもしれません。歴史を紐解けば、昭和30年代後半に東京駅からの路線として開業し、その後すぐに新小岩駅発着に短縮・変更されたものの、都営新宿線開通前の一之江周辺エリアの重要な足として長らく機能していましたので、往時はこの折り返し場にも次々とバスがやってきて、活気を呈していたものと思われます。

帰りのバスまで、まだあと1時間少々。もうしばらくこの折り返し場に、身を置くこととしましょう。廃止を惜しむ大勢のファンが詰めかけた東横線渋谷駅とは対照的に、人知れず静かに廃止の日を迎えようとしている「春江町終点」の姿は、じわじわと染み入るように私の脳裏に浸透し、記憶の印画紙にしっかりと焼き付けられていきました。

- 岩垣 顕
- 雑司が谷の杜から 東京再発見への誘い
- 歩いて完乗 あの頃の都電41路線散策記
- 1967年生まれ。坂、川、街道、地名、荷風など、様々な切り口で東京の街歩きを楽しむ散歩人。著書に、「歩いて楽しむ江戸東京旧街道めぐり (江戸・東京文庫)」「荷風片手に 東京・市川散歩」「荷風日和下駄読みあるき」など。


 あなたの知らないデンリョクの世界(その1)
あなたの知らないデンリョクの世界(その1) ナイスマンホ!な商店街 その1
ナイスマンホ!な商店街 その1  焼き物の里・信楽へ、真夏のホーロー探検
焼き物の里・信楽へ、真夏のホーロー探検 東京銭湯王国・北千住銭湯巡礼 その弐・西口編
東京銭湯王国・北千住銭湯巡礼 その弐・西口編 夜の暗渠歩き
夜の暗渠歩き 日本一の鍾馗ストリート
日本一の鍾馗ストリート おまえのことは俺がいちばんよく知っている、という種類の愛
おまえのことは俺がいちばんよく知っている、という種類の愛 北鹿浜公園:最新のミニ列車が走る交通公園
北鹿浜公園:最新のミニ列車が走る交通公園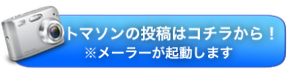
 2011.07.02 「マニアパレル」歯車&廃線
2011.07.02 「マニアパレル」歯車&廃線
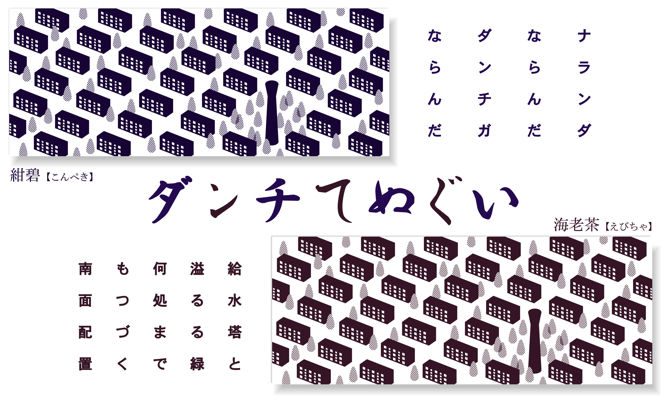 2010.06.21 マニア向けアパレルで「マニアパレル」
2010.06.21 マニア向けアパレルで「マニアパレル」
 2010.12.18「株式会社 東京地図研究社」(前編)
2010.12.18「株式会社 東京地図研究社」(前編)
 2010.12.23「株式会社 東京地図研究社」(後編)
2010.12.23「株式会社 東京地図研究社」(後編)
 「東京時層地図」
「東京時層地図」 「TOKYO古地図」
「TOKYO古地図」 「ロケタッチ」を使い倒す!
「ロケタッチ」を使い倒す! 「ロケタッチ」
「ロケタッチ」